大家好,我是Kyo桑。
今日Kyo桑要以身為本多流門人的身份,來簡單介紹於昭和七年(1932)由師範會制定之本多流「七道」內容。
これより此一本の矢を射る順序と規矩とを御話しいたしませう。
この一本の矢をひくにつきての法則は巳に中古大なる改良がありました。就中、 日置彈正政次の定めたる法則は今日まで残りて廣く行はれて居る次第でありますから、先ず 此人の工夫に成れる法則や順序をお話致すこととしませふ。
此人は先ず七道といふ法則を立てたのであります、その七道と申すことは 一に足踏、二に胴造、三に弓構、四に打起、五に引取、六に會(會のことを流派によりて持の 字を用ひますし又抱へとももうします。)、七に離れであります。
之れにつけ加えて五味といふのがありますが、五味とは第一が目附、次が引込み、 次は抱へ、四は離及び延び合、五に見込であります、七道に五味を加ふると申すなれども、 七道の方は姿勢の規矩を現に人の肉目より見て名つけた所で御座います、然るに 五味の方は精神上の働きにつきて定めたる規定でありますから、目に見ゆる所の 七道とは全く性質を異にして居ります、つまり一方は精神にありて他の方は外形に あるのであります、弓を學ぶものは初歩の中より精神を込めてすることが必要なれば、 又此五味を五法といひて之を鍛錬することが肝要であります、そこで先づ目に見ゆる 所の七道から説き初むることに致しませう。
本多流弓道とは、射は剛健典雅を旨とし、精神の修養と肉体の錬磨を以て目的とす。
一、足踏(Ashibumi)
一、左右兩足的拇指尖與標靶約呈一直線。
二、兩足拇指尖的距離以約身高的五成二為基準。(以Kyo桑而言就是約70cm)
三、兩足角度約為六十度(內側)。
一、足踏
一、左右両足の拇指の先は的に向かって約一直線にあること
二、両足先の拇指の間隔は身長の約五割二分位を基準とす
三、両足の角度は約六十度(内側)とす
・蜘蛛の規矩(きく)
・扇の規矩
・闇夜の規矩
二、胴造(Dōtsukuri)
一、身體重心托於兩足,並鬆緩雙肩。
二、上半身稍稍前傾。
三、兩腳膝蓋撐直,兩足內側如同與大地結合般地緊貼。
四、意識沈澱靜謐如林,且保持丹田充實。
二、胴造
一、身体の重みを両足に托し左右肩を落とすこと
二、上体は稍前かがりとなること
三、両脚はひかがみを伸ばし両足裏は大地にぴったり着く様に力を入れること
四、静かなゆるやかな気持ちになり腹の力が抜けぬ様にすること
・大日(だいにち)の規矩
・真の鞍の規矩
・「妻肩(めかた)上肩地紙に重ねよ」
・日月身
・五身(ごしん)五胴
三、弓構(Yugamae)
一、將弓置於左膝內側,左右兩拳自然垂置於正面。
二、「打起」前將面部轉向標靶。其他請參照「手之内」「會」。
三、弓構
一、弓を左の内膝節に立て左右の拳を揃え体の正面にてなすこと
二、打起の前に顔を的に向けること。「手の内」「会」参照
・弓懐(きゅうかい,ゆみふところ)
・三つの規矩
比人双の比の位
墨指の規矩
骨法による弓立所
四、打起(Uchiokoshi)
一、「打起」約四十五度。
二、兩肩維持鬆弛下,將氣力沈澱於臍下丹田處。
四、打起
一、打起は約四十五度に打ち起こすこと
二、両肩が上がらぬようにし精神を落ちつけ臍下丹田に気を収めること
・会(かけ)の弦道
・剛(ごう)の弓懐
・比人双の人の位
五、引取(Hikitori)
一、至「打起」的位置起,左臂朝左斜上方移動,且左肘移至與標靶重疊處;右臂僅前臂轉向標靶方向,右肘約呈直角,且肘點較「打起」時略向上伸張,右拳接近額頭處且勿低於眉;左右拳約處同一高度。此稱之為大三(中力)。
二、所謂「引く矢束の三分の一」是指此時引弓距離應為滿弓距離的一半以上。
三、接著進入「引取」的第二動。左臂推弓,右肘向後迴轉展開,如同身體陷入弓弦間般的將弓引滿。
五、引取
一、打起の位置から左手を左斜に動かし左肘の上辺に的を見る所まで持って行き右手は肘から先だけを左に動かして右肘が直角位に曲がり肘の位置は打起の時よりもすこし高くなって頭に近づけて拳は眉毛より下らぬ様にして左右の拳をほぼ平らにすることこれを大三(中力)と云う
二、この時矢束は引く矢束の三分の一即ち自分の矢束の約半分以上になるべきこと
三、次に引取の第二動に移る左手は弓を押し右手は肘を後ろに廻し身体が弓と弦との間に割り込むようにして矢束を十分に引くこと
・鵜兎の梯(かけはし)
・押し大目、引け三分の一(父母大三)
・真行草
・中(あた)りについて
・引取の遅速
・三心相引
・三つの強弱
六、會(Kai)
一、引取完成處通稱為「會」。
二、此時箭矢應輕貼於耳下至唇間之臉頰處。
三、弓與身形一體且稍稍前傾。
四、統整「會」的同時,確定瞄準位置。右眼(主眼)從弓身內側(左側。西半月)瞄準靶心。左拳與標靶之間的高低差會根據弓的強弱及標靶距離而異。雖瞄準點會因人而異,練習時可請他人於「會」時確認箭矢是否筆直朝向標靶。此時務必事先確認射手頸部是否正確面向標靶。
五、進入「會」時並非表示左右兩臂已停止運動,更是為了接下來的「離」準備。持續保持雙臂、雙肩、胸等延展,且勿使胸肩緊縮、遲緩。此稱為「伸合」。
六、會(会)
一、引取が完了したる所を會と云う
二、この時矢は耳の下より口割までの間にして頬に接すべきこと
三、弓は身体と一致するように稍伏せること
四、會の形が整うと同時に狙いも定まるべき右眼を主として弓の内側(左側)より的の真を狙うべし拳と的との高低は弓の強弱的の遠近によって異なる。狙いは人に依って異なるものであるが人に後方から見て貰って的について居る時の自分の狙いをよしとするその正しい顔の向け方を必要とす
五、會に入ると左右両手の運動は制止するがこれは終局の制止ではなく次に来る離れの為の準備であって左右の手左右の肩胸等が縮んだり緩んだりする事の無い様に努力すること之を伸合と云う
・雪の目付
・一分三界
・着己着界
・狙いの遅速
・五部(こべ)の詰
・八方詰
七、離(Hanare)
一、為產生「離」,以左手拇指推壓中指同時,配合右手拇指強力彈出與無名指(四指弽)分離。
二、右肘展開的角度約以一百度基準。初學者則盡可能大大展開。
三、最重要的是「離」需強力且輕巧。
四、全身氣力滿盈地「會」所產生的「離」,其後仍存有此射餘韻。此餘韻稱為「殘身」。
七、離
一、離をなすには左手の親指をしめて中指に押しかけこれと共に右手の親指を強くはね無名指と分離せしめるのである
二、右肘の部分の開いた角度は約百度位を基準とす初心者はなるべく大きくすること
三、離は強くして軽きことが肝要である
四、會の時の全身の気力充溢の余韻が離の後に存在すべきで之を残身という
・四部の離
・鸚鵡の離
・雨露利の離
・四個(しか)の離「切・拂・別・券」
・六凶(ろくき)の離
「手之内」
「手之内」是左手的「取懸」,「會(kake)」是右手的取懸,並同時構成「弓構」。「弓構」時,「手之内」拇指與中指將弓環住,並將無名指、小指貼於中指側,拇指腹緊密地扣於中指第三關節上。中力(大三)後,「引取」拇指與食指間推壓弓身,中指與拇指圈住弓身,並維持與弓身間呈現直角,以拇指根部推壓弓身內竹右側,此稱為「中押」,為正確持弓推弓之理。
「手の内」「會」
手の内は左手の取懸け會は右手の取懸と思い共に弓構の場合に行うべきもの手の内は拇指と中指で弓を握りそれに薬指小指を添へ拇指の腹が中指の第三関節の所に懸け指の間に隙を生ぜぬ様になすこと
中力以後引取にかかっては拇指と人差指との股で弓を正面に押し中指と拇指とで出来た輪の形を以て弓に直角の気持ちで押しかけ拇指の根元で弓の右内側を押しぬくこと之が中押と云って正しい弓の握り方であり押し方である
・五加
・鵜の首
・卵中
・三毒
・骨法
・呼立(ああたったり)
・定恵善
「取懸」
以弦枕勾弦,以帽子頂端卡在無名指第三關節(四指弽。三指時則為中指第二關節處)處,且從外側可稍稍看見的程度。食指、中指以無名指為準,輕貼於其上。箭矢介於食指中段處,由食指從箭身外側輕壓之。中力(大三)後「引取」的同時,帽子內拇指傳以向上撥彈狀之力。以最小限的力量引弦,弦、會口(kakeguchi)、箭矢呈一體的狀態(気持ち)之時,將拇指撥彈出,使弦釋放。
取懸方
弦枕の所に弦を引かけ帽子の頭を薬指の第三関節の所に帽子の先端が外部より少し見ゆる程度に懸け人差指と中指とは薬指に準じ軽く添え矢は人差指の中頃の高さにし人差指の根元で外面より軽く矢を支えること中力以後引取りに懸る時は帽子の中の拇指は上にはねる様に力を入れ弓の方へ引かれる弦の力と最小限の力を以て引き来たり弦と會口と矢と一緒の気持ちで拇指をはね起して弦を放ちやること
・一文字、十文字
・恵休善力
・浅深
・弦計
分類:本多流
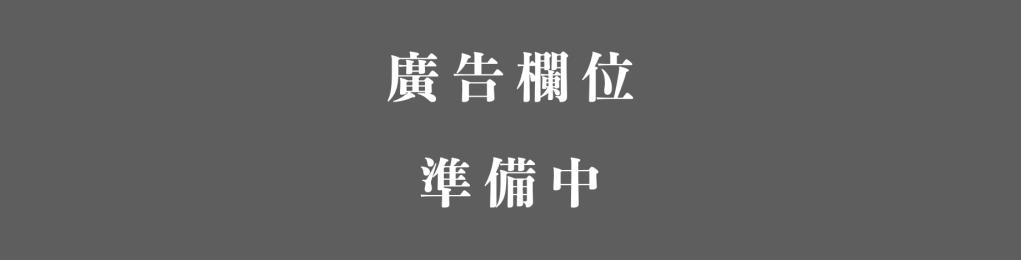
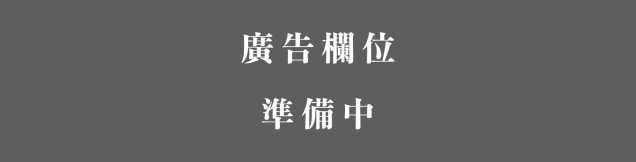
1 replies »